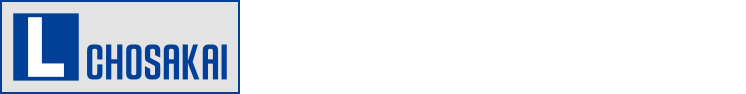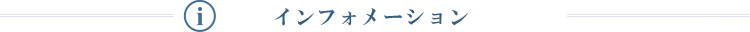労働あ・ら・かると
この1年、あなたは年休を何日取得されましたか~10月は「年次有給休暇取得促進期間」です 完全取得目指そう~
労働評論家・産経新聞元論説委員・日本労働ペンクラブ元代表 飯田 康夫
〇労働あ・ら・かるとを閲覧される皆さまに問いたい。あなたはこの1年間に年休(年次有給休暇)を何日取得されたでしょうかーと。年休20日から25日取得したという人もいれば、半分くらいかな、いやほとんど取得していない、年休はいざという時のために残すものだという古い考えを持つ人、職場で年休取得を言い出せる雰囲気にない、あるいはパートさんには年休はないと上司に言われ、安易に納得していたという人など様々であろう。取得率でみても、ほぼすべて取得したという人もいれば、半分くらいかな、いやまったくゼロ%だという人などこれまた様々だ。
〇忙しくて休暇を取るヒマもないという御仁もおられよう。一方で年休取得は権利だし、しっかり計画をたて、完全取得している人、会社挙げて年休取得を推進しているケースもあれば、労組が常に組合掲示板に組合員の年休所有日数を掲げ、計画的に年休取得を決め、良き慣行を実行しているケース。新年早々社員大会で、社長と従業員全員参加の大ジャンケン大会で勝ち抜いた順に年間の年休取得日を優先的に確保、年休完全取得を実現している企業など知恵を出すことで年休の取得率は高まるようだ。だが、中には年休が取れる職場の雰囲気がなく、我慢している人、会社に請求してもいい顔をしてもらえないので遠慮しているなどこれまた様々だ。
〇そういえば10月は、厚労省の呼びかけで「年次有給休暇取得促進期間」とされている。ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年休の取得を促そうという運動だ。
〇過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和6年8月2日閣議決定)で、令和10年度までに、年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられた。最新のデータでは、令和5年の年休の取得率は65.3%と長年50%以下だった取得率がここ数年の間に上昇を見せ、過去最高となっているものの、目標には達していない。しっかり働き、ゆっくり休むというワーク・ライフ・バランスの実現のためには企業労使が自社の年休取得の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを推進していくことが重要だとされる。
〇政府の年休取得率目標を達成するためには、どう取り組めばいいのか。厚労省からは、①年休の計画的な付与制度の導入ー年休の付与日数のうち、5日を除いた残り日数について、労使協定を結ぶことにより計画的な年休の取得日を割り振れる制度と②時間単位年休の導入―年休の付与は、原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができることが参考となる。
〇厚労省では、年休取得促進に向け、特設サイト、WEBマガジン「厚生労働」、「人事マガジン」での広報・情報発信をしているので参考にしてほしい。
〇年次有給休暇取得促進サイトでは、年休を取得しやすい環境を整備するために役立つ情報を提供しているので、一度クリックしてほしい。「リーフレット」もダウンロードできる。たとえば岩手労働局のリーフレットでは「年次有給休暇を活用して岩手県の魅力に触れよう」と呼びかけ、秋田労働局のリーフレットでも「年次有給休暇を活用して秋田県の魅力に触れよう」と呼びかけ、福岡労働局のリーフレットでは「働きやすか福岡」と博多なまりを活かした年休取得促進を呼びかける。
〇働き方・休み方改善ポータルサイトを覗くと活用のステップが紹介されている。
〇診断の指標として、①働く時間の適正を、②労働時間に課題のある社員の状況、③休暇の取得状況、④休暇取得に課題のある社員の状況、⑤定時退社の状況、⑥連続休暇の取得状況、⑦テレワークの状況、⑧勤務時間の柔軟化、⑨時間制約のある社員の活躍の9項目をチエックし、その結果を点数化し、年休の取得促進への指針とされたいというものだ。
〇労働者1人平均付与日数16.9日、取得日数11日、取得率65.3%
〇ところで、最新の年休の付与、取得の実態どうなっているのかをみたい。
〇厚労省の賃金労働時間制度調査令和6年版によると、令和5年1年間に企業が従業員に付与した年次有給休暇日数(繰り越し日数を除く)は、労働者1人平均、16.9日(令和5年度調査では17.5日)。このうち労働者が取得した日数は、11.0日(同10.9日)で、取得率は65.3%(同62.1%)となっており、昭和59年以来では、もっとも高くなっている。年休取得率を産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」が71.5%でもっとも高く、次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が71.1%、「電気・ガス・熱供給・水道業」が70.7%、「製造業」が70.1%と続き、この4産業が7割台だ。もっとも低いのは「宿泊業・飲食サービス業」が51.0%、「教育・学習支援業」が56.9%で、残りの「建設業」や「情報・通信業」、「運輸・郵便業」、「卸売業・小売業」、「医療・福祉」などは60%台だ。
〇年休取得日数でも、多いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」の13.2日、「製造業」の12.9日、「鉱業、採石業、砂利採取業」の12.7日などで、少ないのは「宿泊業・飲食サービス業」の5.9日だ。産業別で大きな差が見られる。
〇年休取得率の過去の推移をみると、平成13年当時の49.5%から同17年と19年の46.6%を底に同30年まで、18年間50%に満たない水面下にあったが、同31年に51.1%へと久しぶりに50%台に回復。その後は働き過ぎの反省から令和を迎えて、ようやく、取得率は上向きとなり、令和5年には62.1%へと6割台を記録、同6年65.3%に至っている。
〇ここで、取得率をめぐり勘違いをしている日本の労組幹部の苦い思い出話を紹介したい。わが国では、年休取得率がとかく話題となるが、EUなど先進国は、どうなっているのだろうか。ひと昔以上昔の話だが、ある労組幹部が欧州へ労働時間制度の調査団を派遣した時の欧州労組とのQ&Aで双方が思わぬ勘違いをしていることが分かり、日本の常識が極めて非常識であるかを思い知らされたことがある。それはこうだ。「あなたのお国では、年休の取得率は何パーセントでしょうか」と日本側が質問、相手国は、何を聞くのだという怪訝な様子。年休は100%取得が当たり前で、取得率という言葉が理解できなかった様子。日本では年休は残すもの、取得率はせいぜい50%程度が当たり前の時代、これが日本の常識。ヨーロッパ諸国では年休はすべて取得するのが当たり前の常識。日本のように年休を残す、取得率を上げるという感覚がヨーロッパ諸国では存在しないだけに、相手国の労組幹部は、日本で常識とされる取得率を議論することなどありえないというわけだ。恥をかいた感じの日本の労組幹部は、反省しきりだったとか。
〇このように、日本では年休が取得しにくい環境にあることがわかる。取得しにくい条件は企業側にも従業員側にもあるようだ。「忙しくて年休を取得する余裕がない」とか「周囲の目が気になって取得しにくい」などの話をよく聞く。
〇パートさんからの声として「わが社のパートには有給の休暇制度はない」と上司に言われたとか、「年休を取得しようとすると、いちいち取得する理由を説明しないと取得が許されない」、「見ての通り、いま会社は超多忙だから年休は遠慮してほしい」などだ。ただ、企業側には、仕事が立て込んでいて多忙であるときなどには、時季変更権が認められている。一方、パートには年休はないという発言は、労働基準法違反で、あらゆる働き方を問わず、年休は「一定の条件を満たせば(6か月以上勤務し、出勤率が80%以上)誰にでも付与されることが労働基準法に明記されている。」
〇従業員側に問題がある場合もある。業務量を抱え過ぎていて年休をとることもできない場合、自らのスキル不足から年休が取れない時も、上司や先輩が年休も取らず、頑張っている姿をみて年休を言い出せない雰囲気がある場合などだ。
〇そうだ、あなたは労働基準法を詳細に読み取った経験があるだろうか、ざっと目を通した程度かは別にして、労基法は働く人の最低基準の保護を目的にしていることはご存じであろう。では、労基法の年次有給休暇を規定している第39条の主語は労働者か使用者かご理解されているだろうか。労働者保護規定だから「労働者は年休を付与され取得することができる」と解釈されてはいないだろうか。主語は使用者は~~となっていることを再確認してほしい。
〇そこには、「使用者は~~10労働日の有給休暇を付与しなければならない」と明記されている。さらに②でも「使用者は、~~(勤続経験の積み重ねを)加算した有給休暇を与えなければならない」とし、④でも「使用者は~~有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」など主語は使用者に厳しく“与えなければならない”と明記されていることを改めて読み返してほしい。