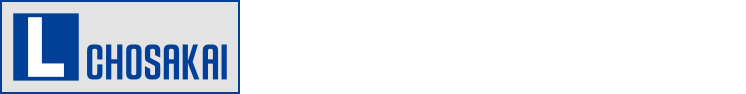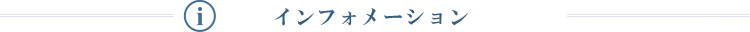労働あ・ら・かると
シルバー人材センター活用の思い出
一般社団法人 日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
〇少し前ですが、宅配事業者の物流ターミナルを見学する機会を得ました。
〇最近の技術進歩のご多分に漏れず、ベルトコンベアーの上をかなりのスピードで段ボール箱が走り、伝票のバーコードやQRコードを読み取って自動的に仕分けし、配送先ごとに峻別していく光景にはごくわずかの人影しか見えませんでした。
〇最新鋭の機器による配送品の流れを見ていると、1980年頃だったと思うのですが、当時の配送作業の現場の記憶がよみがえってきました。
〇当時始まったばかりで今ほど法律などのルール整備が十分でなかったのですが、某市から当時民間企業で労務担当をしていた筆者の勤務先に「シルバー人材センター」の利用要請があったのです。
〇当時の筆者勤務先では、暮れの繁忙期に荷捌き量が急増するので、その発送先を分別する作業を配送倉庫にて労働集約的に行っており、今ほどの人手不足ではなかったものの、年末のこの時期の学生アルバイトなどの臨時労働力の確保には、それなりの努力と工夫が必要でした。
〇筆者としては、新しい動向に興味がありましたし、このセンターの活用を試みようと思い、担当の方とお話しして約50名のシルバー人材を3週間ほど依頼しましたが、なにしろ初めてのことですから、面食らうことが続出しました。
〇まず、採用面接はしないで欲しいとのこと、まぁ学生アルバイトを雇う時でも面接選考しているわけではないので、全ての方に就業していただくことにしたのですが、センタ-のご担当曰く「ウチは職業紹介事業ではないので、個々人の登録者の軽作業の業務委託をご紹介していることになります。」とおっしゃるのです。
〇配送作業の現場責任者は、筆者に「コヨウでもイタクでもなんでもいいから人手を確保してくれ。」と言いますし、その気持ちも判るのですが、新米労務担当だった筆者は、改めてアルバイトを確保するにあたっての「雇用と委託の違い」を調べ、当時懇意にさせてもらっていた労働基準監督署の方にも相談しました。
〇もう時効でしょうが、今思い出しても実態は「雇用」の「委託と称した」人材確保策の問題点に50年近くも前に直面していたということになります。
〇筆者の上司は、「地方自治体からの要請なのでなんとか協力策を考えるように」と言いますし、腕組み思案をした筆者の結論は「一番の問題点は労災保険の適用がないことだ。」ということで、知り合いの損害保険代理店に話をして、シルバー就労者全員が就労期間中の障害保険に加入して保険料は雇用主ならぬ使用者が負担することにしました。
〇その分学生アルバイトよりは見かけ上はコスト増になったわけですが、経費予算担当者をはじめ社内関係先に「その分労災保険料はかかりませんから」と説得して回った記憶があります。
〇幸い傷害保険の申請をする事態は起きませんでしたが、高齢者の方(といっても当時のことですから61-62歳の方々)に働いて貰う際の留意事項について、気づきをたくさん得ることができました。
〇就労初日、学生アルバイトと混在して作業をしてもらったところ、問題が早速発生しました。コンベアを流れてくる発送品貼付伝票の宛先を肉眼で読み取って、取り上げる取り上げない作業の速度が大きく異なり、流れてくる発送品の伝票を目を凝らして追いかけてしまい、一緒に動いてしまうので、学生アルバイトとぶつかってしまうのです。
〇配送作業現場責任者は「全員若いアルバイトにしないと事故が起きてしまう。」と不満たらたらでしたが、筆者としては地方自治体に協力する必要があり、間に挟まって困惑した記憶も甦ってきます。
〇対策としてコンベアレーンにシルバー人材と学生アルバイトを混在作業させることを止め、シルバーだけのレーンとし、要望を入れて回転速度を少し遅くして、照明を増設する方策を実施しました。今、自分の老眼白内障に苛立つことのある筆者は、ますます当時のシルバー人材の気持ちが分かるようになったのですが、当時は未熟で、言っていただけなければ分からなかった改善策を提案してくださったシルバー人材の方への感謝の気持が、改めて湧いてきます。
〇因みに新米労務担当だった筆者に、このようなことを諸々教えてくださったシルバー人材の方は、中堅物流業で人事部長を最後に定年退職した方で、筆者勤務先の大株主だったことが後日判明し、再々度のけぞって頭の下がる思いをしたものです。「退職金に手をつけずに孫へのお年玉稼ぎができます。」と明るくおっしゃっていました。
〇筆者の推測ではありますが、あれから50年近く経過した今、団塊の世代は後期高齢者となり、定年延長再雇用制度をはじめとして企業の高齢者活用が進んだ結果、「シルバー労働市場」に輩出されてくるシルバー人材の数は減少しているはずですし、急速に拡大しているスポットワークにて就労する高齢者の増加を見ていると、今のシルバー人材センターは、人材確保に腐心していらっしゃるところもあるのではなかろうかと思います。
〇労働力不足や、スキルやスキマ時間を持つ高齢者の増加といった社会課題を背景に、センターが今後果たすべき役割は、単なる「仕事の提供」から「地域社会の活性化」や「多世代交流の拠点」などへのシフトではないか、と考えたりします。高齢者の生きがいと社会貢献を結びつける、未来のモデルが構築できるかどうかが課題なのだろうなどと想いをめぐらせています。
〇以上
〇(注:この記事は、岸健二個人の責任にて執筆したものであり、人材協を代表した意見でも、公式見解でもありません。)