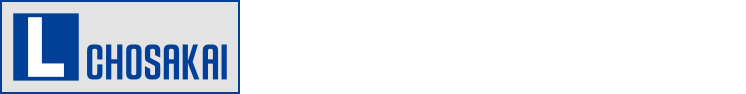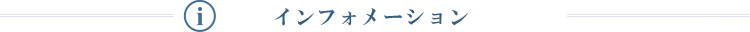労働あ・ら・かると
年休は「預り金」だと割り切ろう
社会保険労務士 川越雄一
〇4月に入社し、今月1日に年休(年次有給休暇)が付与された従業員も多いのではないでしょうか。この年休、会社から恩恵的に与えるようなイメージもありますが、実際には要件を満たせば当然に発生します。会社にしてみれば「預り金」のようなもので、そのように割り切れば、今の時代における年休への対応も見えてきます。
1.どこか似ている預り金と年休
〇預り金というのは、会計の勘定科目に用いますが流動負債に当たります。一方、年休も要件を満たせば当然発生し、従業員から請求された期日に取得させなくてはならず、この二つどこか似ているところがあります。
●預り金は返金または支払い義務がある
〇預り金とは、将来の返金または支払いを目的として、一時的に預かっているお金のことを指します。貸借対照表では右側、流動負債の部に記載されます。ポイントは「一時的な預かりである」ことと「返金または支払い義務がある」ことです。従業員から天引きした税金や社会保険料などがありますが、決算では精算されるのが原則です。
●年休は当然に発生する
〇年休は恩恵的というか福利厚生のような感じもしますが、そうではなく6カ月継続勤務(2回目以降は1年)と、直近の1年間に8割以上出勤で当然発生(付与)します。ですから、働きぶりが良いとか悪いとか、退職日直前の従業員でも要件を満たせば発生してしまいます。また、従業員からの年休請求は休む日を特定するに過ぎないとされています。
●年休未消化分は債務
〇「国際会計基準」では、その年に従業員に対して付与された年休のうち、未消化分を、企業が負うべき債務と考え、「年休引当金」として債務計上が義務付けられています。未消化の残日数に対して各従業員の日給を乗じて金額を算出します。日本の会計基準では計上できませんが、従業員から請求されたら与えることが必要なので実質的に債務みたいなものです。
2.年休を恩恵的な制度と捉えると
〇年休を預り金ではなく、会社の恩恵的な制度として捉えると、できるだけ年休を取らせない対応になりかねません。しかし、昭和の時代ならともかく、令和の今は会社にとって得策ではありません。
●年休願いにより会社が承諾
〇年休取得が「年休願い」ということになっていて、ご丁寧に年休を取得する理由まで書かせている場合があります。そして、これらの内容を見て会社が年休取得を承諾するカタチになっています。たしかに法律上は、年休取得日の変更権は会社に認められていますが、そのハードルはかなり高く、また、年休中に何をするかは不問となっています。
●抑えつけは逆効果
〇昭和の時代にはお局(つぼね)さんみたいな上司なり総務担当者がいて、年休を取りにくい雰囲気を醸し出していました。このような抑えつけは誰にでもできることではなく、その人の持ち味だったのでしょうし、本人も「会社のためになる」と思い込んでいたのだと思います。しかし、今の時代、その抑えつけは逆効果で会社の印象を悪くするだけです。
●「休みにくい」と「休む」
〇従業員というのは年休で「休みにくい」と、突然「休む」ものです。休み慣れていないので休みのマナーを知らないのかもしれません。逆に、日頃から年休で「休ませる」と、計画的に「休む」ものです。人の心理として、禁止されると逆にそれをやりたくなります。例えば、「体をそのまま動かすな」と言われた途端、動かしたくなるのと同じようなことです。
3.年休残日数はできるだけ減らしておく
〇年休を預り金と捉えれば、近いうちに休み(金銭の支払いが発生)を与えなくてはならないわけですから、日頃よりできるだけ日数を減らし身軽にしておくことが得策ではないでしょうか。
●キチンと年休管理をしておく
〇年休と適切につき合う第一歩は年休管理です。前期からの繰越が何日あって、今年何日発生し、この1年に何日取得し、今期末には何日残っているかを明確にします。このような内容が記載されたものを「年休管理簿」といいますが、あったほうが良いではなく会社に作成義務があります。また、3年間の保管義務もあります。
●日頃から取得を促す
〇年休もまとめて取得されると困るので、日頃から小まめに取得させておくことが肝要です。日頃から取得させておくと、そう見境なく突然年休を取得するようなことはしないはずです。また、「労働時間等見直しガイドライン」によると、年休管理簿を作成したうえで、その取得状況を労働者本人および上司への周知が求められています。
●退職時はキレイさっぱり精算する
〇年休を日頃から取得させておくとは言うものの、忙しかったり小規模な職場ではそれもままなりません。もちろん、退職時に年休消化で休む人もいますが、遠慮してそのようなことを申し出ない従業員もいますから、そこを察して会社から年休残を買い取るのも手です。こうすることで「言ったもん勝ち」の職場になることを防げます。
〇年休というのは、昔から話題になりやすい制度ですが、令和の時代に言えることは「年休は預り金」だという割り切りであり、そのことが人材獲得・定着にとってとても重要であるということです。