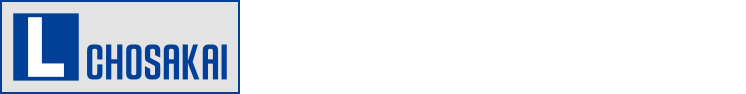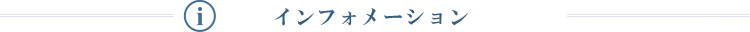労働あ・ら・かると
「ルール・マナー・モラル」に想い巡らす
一般社団法人 日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
〇筆者の仕事のひとつに、職業紹介事業者に選任が義務付けられている「職業紹介責任者」に対する講習の講師があります。
〇ほぼ丸一日の講習の午後を担当しています。講義の内容の軸は職業安定法などをはじめとした労働関係法令に定められた、職業紹介に関連することです。
〇講習の会場でも、オンラインで実施をしていても、受講生からさまざまな質問を受けるのですが、その姿勢や発想に愕然とすることが残念ですがあります。
〇考え過ぎなのかもしれませんが、その質問の背後に「どうすればその法律をくぐることができますか?」という発想が見え隠れするような気がすることがまれにですがあるのです。
〇有料職業紹介事業は厚生労働大臣の許可が必要なビジネスであることは、読者の方々はご存じでしょう。筆者は講習の中で、たとえ話として自動車運転免許制度を取り上げます。
〇「運転免許を取得することと、上手に無事故運転を続けることの差をご理解いただきたい。」「ルールを守らず事故を起こしてしまえば、他人を傷つけることになるし同乗者にもけがをさせるかもしれないということを忘れずに、職業紹介に従事してください。」というようにお話しします。
〇辞書や生成AIを調べると、ルールについては「社会や組織であらかじめ明文化され、守ることが強制される決まりごと。」「法律や校則、スポーツの競技規則など、違反すれば罰や不利益がある。」と解説されます。
〇法律上の禁止事項や行政指導の説明の後、「みんなもやっていることなのに、なぜ捕まるのですか?」という率直な質問を受けた時には「速度違反でパトカーに捕まった運転手が『みんなもこのくらいのスピードで走っている。』と主張するのに似ていますね。」と回答し、「なぜ速度制限があるのか考えてみましょう。事故防止のためですよね。」と説明します。
〇ルール(法律)に反しなければ、何をやっていいのかと言えば、罰則がなくても守ったほうがよい「マナー」というものがあると思います。「マナー」というのは、自分以外の人への配慮から求められるものだと思います。
〇順番を守って並ぶ、電車で大声を出さない、傘をさしてすれ違う時に傾げる、若い元気な方はシルバーシートを必要とする方に譲る、など具体的な場面を思い浮かべると、「最近は守られないことが多くなっているような。。。。。」とも言いたくなります。
〇更に考えると他人との関係性がなくても守ろうとするのが「モラル/倫理・道徳」と考えてもいいでしょう。
〇整理すると
〇ルール=「守らないと罰を受ける」外的強制の決まり
〇マナー=「守らないと周囲に迷惑」人間関係を円滑にする礼儀/他者との関係の中で必要
〇モラル=「守らないと自分の良心に反する」内面的な倫理/人が見ていなくても/道徳的な自戒
〇ということでしょうか。
〇法律の条文に書いてなくても、あるいは罰金や拘禁刑といった罰則のない規定であっても、何でもやってもいいというものではないのに「破るとどんな罰則がありますか?」と質問する瞳の奥に「守らなくてもいいや」「処罰されなければいいや」という脱法発想が見えてしまうのは考えすぎでしょうか。
〇紛争が多発すると、処罰付きの法の規制が強化されるのは、歴史を見ればわかることですが、ルールが増える一方で、マナーやモラルの位置づけが薄れているように思えて仕方ありません。
〇モラルがなければ、マナーが薄れれば、いくらルールがあっても形骸化することもあるのではないでしょうか。
〇以前にも申し上げたことがあるかと思いますが、昭和の職業安定法の有料職業紹介の許可条件について調べてみると、古書店で入手した昭和27年版の六法全書(有斐閣)によれば、当時の職業安定法第32条第2項には「労働大臣が、前項の許可をなすには、予め、許可申請者についてその資産の状況及び徳性を審査するとともに、中央職業安定審議会に諮問しなければならない。」とあります。
〇実際にどのように「徳性を審査」していたのか、生成AIに聞いてみてもすっきりした解は見つからず、いろいろ調べた結果判ったのは「『徳性』という文言は非常に曖昧で恣意的運用の余地が大きいため、憲法上の職業選択の自由(憲法22条)との関係でも問題視され、その結果、後年の改正で『徳性』という表現は削除されて、資産要件や欠格事由(破産者、禁錮刑以上の刑を受けた者、暴力団関係者等)といった客観的基準に整理された。」ということでした。
〇筆者が「徳性ある」という単語を聞いて思い浮かべるのは「ルール(法律)を守るだけでなく、マナーもモラルも有している姿」です。戦後の職業安定法の立法に携わり昭和の行政を運用された先輩達の想いを、令和の現在においてどのように実現すべきか、悩ましいところでもあります。
〇以上
〇(注:この記事は、岸健二個人の責任にて執筆したものであり、人材協を代表した意見でも、公式見解でもありません。)