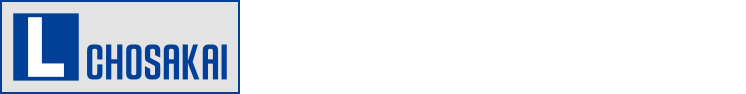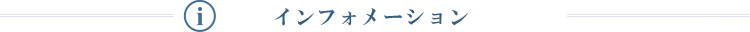労働あ・ら・かると
2年連続5%台の高率賃上げも、物価高騰にたじたじ
労働評論家・産経新聞元論説委員・日本労働ペンクラブ元代表 飯田 康夫
〇~賃上げ、働く者全てに行き渡らず、格差は拡大。要求姿勢に課題~
〇2025春闘は、33年ぶりに高率の賃上げとなった2024年春闘相場(5.33%、厚労省調べ)に匹敵するか、それを上回る水準で終盤を迎えている。連合の最終回答集計(7月3日現在)によると、加重平均で16,356円、率で5.25%(昨年同期比額で1,075円増、率で0.15㌽増)となり、先に開いた第95回連合中央委員会で「5%以上という基本方針の目標を達成し、昨年以上の賃上げに、幅広い産業で積極的な賃上げ要求を掲げ、粘り強く交渉を重ねてきた結果だ」との中間まとめをしている。経団連の集計でも回答妥結状況で、「加重平均額19,342円、率で5.38%」とまとめ、春闘交渉時の十倉会長も「連合とは多くの点で考え方が一致、“闘争“というより”共闘“した実感があり、大幅な賃金引上げの実現という結果につながった」など労使それぞれに、5%台賃上げに一定の評価をしている。
〇だが、これら5%台の賃上げ対象となった労働者は、組織率僅か16.1%という連合傘下の労働組合員、経団連加盟の大手企業の労働者であり、日本列島各地で働く、すべての人たちが5%という賃上げの恩恵を受けているわけではない。賃上げゼロ組もあれば賃上げ率1~2%という中小零細企業の労働者も多く、それは厚労省の毎月勤労統計調査で、その実態を知ることができる。この毎勤統計を読み解くと、例えば2025年5月分の現金給与総額は、企業規模30人以上で33万5,164円、前年同月比0.3%増に過ぎない。4月から5%強の賃上げがあったはずが、収入増の実現どころか、辛うじて対前年同月比でプラスが51か月続いてはいるものの、賃上げ率5%はどこに消えたというのか。米価をはじめ庶民が日常的に必要とする食材などの物価高騰が続く中、実質賃金は春闘直後の5月分でマイナス2.9%だ。春闘を挟んでここ5か月連続マイナスという数値がその実態を私たちの目の前にさらけだす。
〇何のための2025春闘だったのか。一部大企業と労組に組織化されている連合の組合員だけの戯れか。多くの未組織労働者や非正規労働者、中小零細企業に働く労働者そっちのけの労使交渉にやっかみも含めて白々しい雰囲気がただよっている。
〇連合の芳野会長は、先の中央委員会で「実質賃金の状況をみると、生活向上を実感できるとは言い難いこと、企業規模間格差の拡大に歯止めがかかっておらず、適切な価格転嫁や適正取引の実現に至っていない現状にあること、今も春闘は継続中であることから引き続き組織全体として取り組みを進めよう」と強く訴えたが、現実は賃上げが広く働くものすべてに波及しているとは言い難い状況だ。
〇これら勤労者の所得のありのままの姿を明らかにする毎月勤労統計調査は、国の重要な統計調査と位置付けられ、その前身を含めると大正12年(1923年)から始まっているとされ100年選手の肩書を持つ基幹統計調査なのだ。
〇そこでは、賃金・給与はじめ労働時間及び雇用の変動が明らかにされ、景気指標の重要な位置を占める統計なのだ。その最新版2025年5月分の毎月勤労統計調査速報が7月7日公表されたばかり。そこに現れた勤労者の賃金・給与の生の姿を読み解くと、一般労働者とパートタイマーの就業形態計の名目賃金は、1人平均現金給与総額は、規模5人以上で300,141円、対前年同月比1.0%増、41か月連続プラスと記されている。
〇一般労働者の現金給与総額は、384,696円、対前年同月比1.1%増、50か月連続プラス。パートタイム労働者の時間当たり給与は1,382円、対前年同月比4.0%増、47か月連続プラスだ。
〇問題は、実質賃金指数にある。消費者物価指数は、対前年同月比4.0%上昇し、実質賃金は2.9%減と記載されている。これでは、春闘で努力するものの、生活向上には結びつかず、庶民の声として、「生活にゆとりがなくなった」との嘆き節が聞こえてくる。
〇その現実の姿が7月14日に発表となった日銀の「生活意識に関するアンケート調査」(全国の20歳以上の個人2,016人対象)で如実に描き出された。
〇それによると、「景況感」では、「悪くなった」が70.5%と1年前の55.1%を大きく引き離し、「暮らし向き」では、「ゆとりがなくなってきた」が過去の調査で50%台だったのが、61%へ上昇、2年連続5%台の賃上げも、物価高騰で生活にゆとりがなくなっている現実が読み取れる。とくに「物価に対する実感」では、「かなり上がった」が75.3%を占め、1年後も「かなり上がる」が33.4%と物価に厳しい目を向ける庶民の姿が読める。
〇その物価動向を眺めたい。33年ぶりという久しぶりの高額、高率賃上げ5%も、物価高に追いまくられ、実質賃金がマイナス続き。果たして物価高は今どのような状況にあるというのか。
〇帝国データバンクの価格改定動向調査によると、「7月の食品主要195社」の飲食料品値上げは,2105品目で、前年比5倍に大幅増加するということ。カレールウなど香辛料のほかだし製品などを中心とした「調味料」が1445品目。飲食料品の値上げの勢い伯、前年に比べて強い状態がつづくという。値上げの幅だが、1回あたりの値上げ率平均は賃上げ相場5%の3倍という15%だということだ。単月の値上げ品目数としては3か月ぶりに2000品目を突破、2025年1月以降、7か月連続で前年同月を上回り、連続増加期間としては記録的な値上げラッシュの様相をみせる。これでは、5%賃上げも勝てない7月の値上げ品目の中には、「お菓子類」の196品目。この3月以降では4か月ぶりに単月で100品目を上回り、チョコレートやガム、ポテトチップスなど広範囲にわたるほか、一部で内容量変更を伴う値上げもみられるという。
〇2025年通年の値上げは、11月までの公表分で累計1万8697品目に上り、2024年通年の実績(1万2520品目)を49.3%も上回る。食品分野別では、「調味料」が6108品目を数え、前年の1715品目から、実に256.2%増と大幅に増加。「酒類・飲料」は、4483品目で清涼飲料水のほか、ビール、清酒など広範囲での値上がりとなり前年の7割増。加工食品では冷凍食品やパックごはん、海苔などの値上げが目立つ。
〇値上げ率に目をやると、「酒類・飲料」が20%、「菓子」が19%、「加工食品」が16%、「原材料」が13%、「調味料」が12%、「乳製品」が9%、「パン」が6%など。これでは5%賃上げを歓迎するコメントは御免被りたいものだ。
〇これら値上げの要因を探ると、原材料の価格高騰に加え、光熱費の上昇による生産コスト増、人手不足による労務費の上昇、物流費の上昇などが複合的に重なっていることがわかる。
〇賃金、物価、経済の好循環を狙う政労使の合意も、相次ぐ物価高騰に賃上げが追い付かず、2026年以降の賃上げ要求の組み立てにも、原点に返って物価動向をどう捉え、賃上げ要求づくりに組み込めるのか、トランプ関税で、先行きが見通せない中、業績如何で賃上げに暗雲が漂うなどのブレーキも表面化しよう。2026春闘では物価高騰に負けない賃上げ要求方針が求められようが、現段階でどのような要求基準を構成し、対応するというのか、熱い議論が期待される。