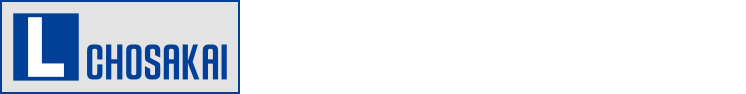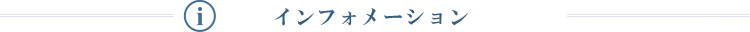労働あ・ら・かると
昭和・平成初期のベテラン人材スカウトを想う
一般社団法人 日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
〇先月「個人情報保護法とホンモノの人材スカウト」を寄稿したところ、何人かの読者の方々からレスポンスをいただいたこともあり、もう少し昔話をさせてください。
〇過日断捨離をしようと書籍の整理をしていたところ、昭和27年版の六法全書が出てきました。書籍整理のときにありがちなことですが、我慢できずに職業安定法のところをめくると、有料職業紹介事業について定めた第32条の第2項に「労働大臣が前項の許可をなすには、予め、許可申請者についてその資産の状況及び徳性を審査するとともに、中央職業安定審議会に諮問しなければならない。」と書かれていました。
〇さて、この「徳性の審査」というのは、具体的にはどのような審査が行われたのだろうという疑問が湧きますが、よくわかりません。
〇少なくとも昭和22年の最初に制定された職業安定法の条文には、「徳性」の文字が見当たらないので、制定後の5年間の間に何かがあって、加えられたのだろうと推測するしかありません。先月、ベテラン人材スカウトの「この仕事は品格がなくてはいけない。」という言葉を紹介いたしましたが、相通じることがあるような気がいたします。
〇そのベテラン人材スカウトは、「スカウト」の意味をよく語っていました。「スカウト」の言葉で脳裏に浮かべるべきなのは「野球のスカウト」「ボーイスカウトのスカウト」だというのです。
〇野球のスカウトという職業は、もちろん野球が好きであることが必須条件ですが、自分がプレイをするわけではなくネット裏でスコアブックを持ち(今はタブレットですね)スカウト対象者をじっくり観察する眼力と将来性を見通せる能力が必要であり、元来軍事用語であるボーイスカウトのスカウト(=斥候/偵察)は、対象や対象を取り巻く環境の状況を正確に把握して本隊に伝えることが重要な任務であって、決して自分が戦闘するわけではなく、むしろ発見されて戦闘になってしまったら斥候としては失敗だというわけです。
〇そこから転じて、人材勧誘の場でも使われるようになったわけですが、当然人材スカウト自身は求人者ではないので、対象人材を雇うわけではなく、同様に自身が、転職して求人内容の仕事をするわけではないという「分際」とでもいうべきところを逸脱してはならないとも、力説していました。
〇また、「人材サーチ」「リサーチ」という言葉の使い方にも慎重であるべきと、強く主張していました。
〇「人材サーチ」のサーチは、サーチライト(探照灯)のサーチであって、「探索する」という意味。「リサーチ(調査)」という言葉を使うと、基本的人権を侵害しかねない身元調査と混同されて誤解を生むというのです。
〇求人者が必要としているのは、候補者が「これから何ができるか」であって、過去に拘泥することは判断を誤ることすらあるとも言っていました。
〇そのベテラン人材スカウトによって転職し、活躍している人材の方との会食に同席したことがあるのですが、その人材曰く「自分では思いが乱れてなかなか決断できなかった。彼は、今いる会社に残ったときの職業人生プランと、スカウトに応じた場合の職業人生プランを冷静に整理してくださった。」ことと「二通りの人生は歩めないのだから、最後はご自分の選択です。」「私(人材スカウト)は伴走者。試合に出るのはあなた。」という言葉を聞き、転職を決意したとのことでした。
〇彼を思い出すたびに、さまざまなコミュニケーションツールが進化普及し、AIが登場している今、人間がかかわって助言・伴走する職業紹介や人材スカウトの価値を見つめなおすことが、ますます重要になっていると思う今日この頃です。
〇以上
〇(注:この記事は、岸健二個人の責任にて執筆したものであり、人材協を代表した意見でも、公式見解でもありません。)