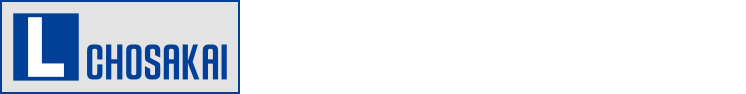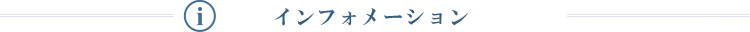労働あ・ら・かると
個人情報保護法とホンモノの人材スカウト
一般社団法人 日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
〇今年は個人情報保護法が施行されて20年になるそうですね。
〇それを聞くと忘れられないのは、その個人情報保護法施行を前に筆者を質問攻めにした、あるベテランの人材スカウトのことです。
〇彼はその更に二十年程前、筆者が民間企業の人事部労務課に勤務をしていたとき、突然電話をかけてきて「貴殿をスカウトの候補者としたい。ついてはランチをご一緒できないか?」としてきた方です。筆者が人材紹介業に興味を持ったきっかけは、この一本の電話だったのです。
〇当時の筆者の職務柄、ILO条約(民間職業仲介事業所条約)の動向などは知識としてはありましたし、第一次石油ショックの際の採用控えによる労務構成のゆがみを是正するため、中途採用の重要性も認識していましたが、まさか自分の身に起きるとは思ってもいなかったので、かなり困惑しながらも生来の野次馬根性が勝って、その人材スカウトとランチタイムを過ごしました。
〇彼は最後まで求人者名を明らかにしませんでした(現在では違法不適切です)が、候補者としての推薦要件は「基幹社員だけでなくパート社員や臨時雇用を含めた様々な労務管理ができること/労働組合と折衝ができること/堪能でなくてもよいが英語に抵抗感のないこと」などなどでした。
〇初めて米系航空会社に搭乗した時に、コーヒーを頼んだらコーラが出てきたトラウマを持つ筆者は、候補者要件(求人要件)を語学力の点で満たさないこと、現勤務先でそう悪くない処遇を受けていることなどを理由に、その日のスカウト話は丁重に断ったのですが、彼の人材スカウトという職業に興味を持ち、その後も年に何度か会食を共にして、人材紹介、人材スカウトのノウハウを聞くようになりました。
〇開発技術者のスカウトでも辣腕を奮う彼は、依頼を受けると、その求人要件の技術領域についての展示会に行って名刺を集めることはもちろん、特許公報を閲覧し、製造業等各社の技報に掲載されたエンジニアの氏名や学会論文の発表者名をリストアップして名寄せし、スカウト対象者リストを依頼者(求人者)と打ち合わせて声をかける順番を決めてスカウトをかける(当時は電話が一般的で、必ずしも違法ではなかった)手法を語ってくれました。
〇その後、筆者が人材紹介業界に転じた後も彼との交流は続き、人材紹介の現場から業界団体事務局に移った後、個人情報保護法が成立し施行を前にしたころ、彼からの質問攻めにあいました。彼の手法がことごとく個人情報保護法違反になってしまうのではないかという状況認識は正しいものだったのです。
〇PC通信が普及し、連絡手段が電話やポケベルから電子メールに移行していったわけですが、彼は「スカウトメールを打つ/送信する」という表現には否定的で、「あんなものは本物のスカウトではない。」と言い続けていました。
〇転職サイト上に、氏名を伏せてとはいえ職務経歴を掲示した人材に連絡をすることは、公共職業安定所に求職登録した人材と求人をマッチングさせることと、彼にとっては同義で、「そういう再就職あっせんも社会にとっては大事だけれど、本物のスカウトは、まだ自分の市場価値を自覚できず転職など考えたこともない人材に対して、可能性の選択肢情報を提供することから始めなければ」というのが持論でした。
〇まるでシャーロックホームズのように、他の人が気づかない要素を組み合わせて人材の転職志向を推理して促していくのが楽しくてしょうがない様子の、彼のニヤリとした紳士面は今でも忘れられません。
〇同時に彼が強調していたのは「この仕事は品格がなくてはいけない。嘘をついてはいけない。」ということでした。彼のその清廉さも、彼にスカウトを依頼する求人者が絶えなかった理由の一つだったのだろうと思います。
〇今年の1月に、「架空の事業者名を名乗った上で、虚偽の事実を伝え、電話応答者を誘導し、当該現場監督者等の携帯電話番号を取得」した職業紹介事業者が、個人情報保護委員会から勧告を受けるという事案が発生したそうです。
〇今となっては、ベテラン人材スカウトの彼は引退し、すでに鬼界に入りましたが、新卒入社社員が早々に転職を意識する時代に変わった今日、彼が存命なら、このような職業紹介事業者が厚生労働大臣許可を保有し続けている事態をどのように語るのだろうかと、思い巡らす夏の暑い夜です。
〇以上
〇(注:この記事は、岸健二個人の責任にて執筆したものであり、人材協を代表した意見でも、公式見解でもありません。)