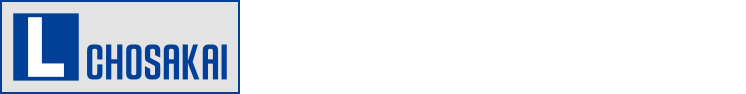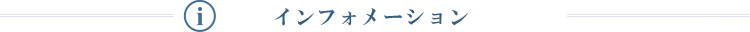労働あ・ら・かると
仲介業は三方よしから七方よしの時代に
一般社団法人 日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
〇職業紹介ビジネスに限らないことですが、仲介業というものは「三方よし」の仕事だと、筆者がこの仕事にかかわり始めたころ先輩から言われたものです。
〇元々は、近江商人由来の経営理念で、「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の三つの視点で経済の循環や社会性を説いたことだと聞いています。
〇人材を企業に紹介することに成功した時、求人者は人材を確保できて「よし」、就職転職した人材は自分を活かせる職場に出会えて「よし」、その間を取り持った職業紹介事業者は、よいお世話ができて「よし」の三方よしというわけです。
〇不動産仲介業界では「売ってよし買ってよし仲介してよし」「貸してよし借りてよし仲介してよし」なのでしょう。
〇昨今は人材ビジネス会社が株式を上場することもあり、そうすると経営者としては、株主に対しては投資して「よし」、社員に対しては今まで以上に「働きがいのある仕事ができて「よし」を意識して企業統治をする重要性が増加しているようにも思います。
〇もちろん経済構造の変化に伴う、円滑な労働移動を推進するという社会性公共性の視点でも「よし」ということを忘れてはならないでしょう。
〇さらにもう一つ考えなければいけないのが取引先などの関連企業です。
〇昭和平成初期までの人材紹介ビジネスは、個人プレーに頼った労働集約的な仕事のしかたが中心でした。毎日20本電話して2~3人の人材と会う約束を取りつけ、企業に対しては求人条件に合いそうな人材を5人ほど提案して、そのうちの一人の採用が決まるという流れの中で、紹介手数料単価にもよりますが、紹介従事者一人当たり年間10~15人の紹介成功があれば採算がとれるというのが、おおざっぱなサイクルだったように記憶しています。
〇しかし現在は、AIの進歩普及を挙げるまでもなく、今やソフトウェアを使わずしてできる仕事ではなくなりましたので、これらの取引先との関係も良好に保つ必要の重要性が増しています。
〇また求職者確保の手法も、電話によるものは姿を消し、ネット上の転職サイトなどを利用するようになり、連絡手段もスマホの普及とともにメールやSNSによるコミュニケーションが主体となっていることは、読者のみなさんに異論はないでしょう。
〇IT技術の進歩により、すべてのビジネスが影響を受け、事業の仕組みが大きく急速に変貌を遂げている中、これらの「七方」に目を配りながら、ビジネスを展開する経営者の方々のご苦労は、並大抵のものではないと思います。
〇株式上場のメリットについては、「資金調達力の向上」がよく挙げられます。
〇昭和平成初期までの人材紹介ビジネスは「小資本で起業できるビジネス」と言われたこともありましたが、今やコンピューターのハード・ソフトの導入整備や維持コストがそれなりに必要なビジネスに転換したので、株式市場を通じての資金調達が魅力的に映ることも理解できます。また、企業の情報公開の義務が大きくなり、社会的信用が高まることに上場する意義を見出す経営者もいらっしゃいます。
〇もちろん創業者利潤の享受という側面も、ストックオプションなどによる従事者のモチベーション向上という側面もありますね。
〇一方で、株主の利益を優先する必要があるため、創業者のこだわりや経営の意思決定の自由度が低下する点も指摘する必要があるでしょう。
〇上場を維持するコストも無視できないと聞きますし、突然の買収リスクにさらされる報道も、他人事ではなくなりますね。
〇人材紹介ビジネスに長く携わってきて、よかったと思う場面、記憶に残る場面を伺うと、上場を果たした経営者の方も、非上場を貫いた経営者の方も、よく口にされるのは、求人者の方からの「良い人材をご紹介いただいてありがとう」との言葉、人材の方からの「自分を活かせる良い職場との出会いを作ってくれてありがとう」という言葉が一番このしごとのやりがい、起業してよかったと思う場面だということです。
〇腰を据えた基幹社員の紹介でも、スポットワークの紹介でも、この点は変わらないことを忘れずに、人材紹介にかかわるみなさんは、これからも事業展開していただきたいと思います。
以上
〇(注:この記事は、岸健二個人の責任にて執筆したものであり、人材協を代表した意見でも、公式見解でもありません。)