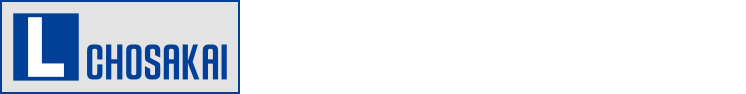労働あ・ら・かると
令和の副業、平成の副業、昭和の副業
一般社団法人 日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二
日本経済新聞の5月20日朝刊一面に「副業解禁、主要企業5割/社員成長や新事業に期待」と大きな見出しの記事が掲載されました。
東証一部上場などの大手企業にアンケートを実施したところ、回答した120社の約5割が従業員に副業を認めていることが分かったとしています。「働き方改革」時代の仕事のしかたが大きく変化していることが見て取れます。
職業紹介の事業相談でも、まだ少なくはありますが「2社に内定して、それぞれ兼業副業OKの企業なので、どのように労働契約を結んだらよいか。」という事例も出てきています。すべてそのようになるかどうかは別として、「令和の時代の働き方」への変化がヒシヒシと感じられる局面です。
平成のはじめの頃、当時職業紹介の現場にいた筆者は、ある人材の転職相談に乗ったことが思い出されます。
その人材はビジネス月刊誌に投稿をしたり、単行本を何冊か出す才能があり、実行していたのですが、勤務先の役員から「副業兼業禁止のルールを知らないのか」とストップがかかったそうです。直属上司は理解があり、「当社での仕事にもプラスの宣伝効果がある。初訪問の客先でも話題のとっかかりになるし、何より自社のことを悪く言っているわけでは全くない。」とかばってくれたそうですが、役員は就業規則違反の一点張りで「企業に所属する意味が分かっているのか。モノ書きになりたいのなら、会社を辞めてからにしろ。」と頑強に譲らず、「勤務時間中にモノをかいているわけではありません。」と言っても「ネタは勤務時間中でも考えているだろう。職務専念義務違反だ!」と怒り出す始末だったそうです。
居心地が悪くなってしまったその人材のご相談に乗っていた筆者は、転職を勧めるかどうか正直迷いました。それなりに好条件待遇の企業でしたし、ご本人も「今モノが書けたからと言って、ずっと書き続けられるかはわからないし、サラリーマンをやっているからこそ筆が進む。」と、とても冷静な自己分析のできている方でした。結論としては、その方は転職せず、但し原稿料・印税の類はすべてその企業の売上げに計上することで、やっとその役員を説得したそうです。今から考えるとずいぶん大げさな話だと思いますが、ご本人が自己実現できればそれでよしとしているのですから、筆者としては深追いしませんでした。後日別の場面でその役員の方が若かった頃、実はジャーナリストになりたかったという話を小耳にはさみ、「何だ。やっかみだったのか。」と思い、また「人材を雇うということは、その人間も家族も丸々抱え込んで面倒を見るということだ。」と発言されている記事を見て、さもありなむと腕を組んだことを思い出します。振返ってみれば、すでに当時、小椋佳さんは銀行員と歌手の兼業をみごとに実現されていた時代ではありますが、まだまだそれは「例外」で、その頃としてはその役員さんの言動・発想はそう珍しいものではなかったようにも思います。
さらに時代をさかのぼって、筆者が企業の人事労務担当だった昭和の話ですが、同期の管理職が困った顔をして相談にやってきました。部下の女性が水着姿かヌード姿で週刊誌に掲載されるというのです。「もしウチの役員が見たら、自分が管理責任を問われるのではないか。」と危惧し、オロオロしての相談でした。人事労務担当として当該女性社員を知らなかったわけではない筆者としては、週刊誌が発売されるとすぐ当人を呼出し、就業規則の副業兼業禁止の条項を読み聞かせました。社名や実名が掲載されたわけではない点は少し胸をなでおろしたのですが、当時の勤務先の体質としては、写真の主が自社の社員であることが役員の知るところとなれば、「何をやっているんだ!」という騒ぎになることは目に見えていたからです。
解雇という強硬手段を選択した場合、訴訟を起こされるリスク、場合によっては「仕事に支障は生じていない。」「業務遂行力に影響はない。」と主張されて、それが労働基準監督署や裁判所で取り上げられてしまう可能性も、当時でもないわけではなく(後日役員にそのリスクを説明して理解を得るには、案の定苦労しましたが)、結果ご本人は「モデルへの道を歩む」と言って、円満退社されたので、一件落着となりました。筆者の脳裏に映るこの昭和・平成・令和の各時代の「兼業・副業」についての考え方がかくも異なるものか、感慨深いものがあります。
これからの時代、例えば地方創生のためのIJUターン人材を確保しようとしても、そう十分に実現できているわけでもなさそうです。そこで、「新しい働き方」として、大都市圏にいる人材の能力・企画力をこの副業兼業、テレワークを活用した形態で地方にて活用する方策も考えられていると伝えられている中、使い古された言葉ですが「発想の転換」をもう一度想い起こすことが、少子高齢化がいやでも進む令和の時代の、人材の能力の引き出し方につながるのではないでしょうか。
(注:この記事は、岸健二個人の責任にて執筆したものであり、人材協を代表した意見でも、公式見解でもありません。)