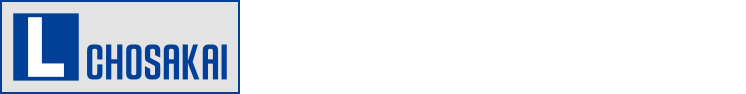労働あ・ら・かると
今月のテーマ(2014年02月 その2)2014年経営労働政策委員会報告について
2月中旬を迎え、労使交渉の動きも活発化している。アベノミクスの政策が反映してか景気に明るさが出てきたとの声が多く聞かれるようになった。円安効果もあって輸出関連企業を中心に企業業績がかなり良くなっているが、輸入関連会社からは業況は厳しいとの話もある。また地方では重苦しかった状況が少し和らいだ感じもするがまだ景気が良くなったとの実感はないとの意見も多い。景気はまさにまだら模様の感じである。
政府は持続的に景気を良くしていくためには、今年は賃上げ(特にベースアップ)が必要で、それを実施することで消費拡大→設備投資→雇用増→賃上げ→消費拡大の好循環サイクルに乗せることを目指すとしている。4月から消費税が上がることもあり、政府は本来、労使自治の範疇である賃金交渉にも異例なほど言動を強めている。
このような動きも背景にあってか、久しぶりに連合や主要な単産、単組はベースアップ要求を掲げ、ベースアップにこだわって交渉し、それなりの結果を出したいと意気込んでいる組合もある。
経営側は例年1月下旬に発表している表記の報告書(89頁)を今年も出版し、経営の諸問題についての考え方を示している。報告書は全体で3章構成となっているが第1章、第2章は後で若干触れるとして、報告書の中心で、多くの人が注目しているのは、今次労使交渉に臨む経営側の考え方を述べた第3章「2014年春季労使交渉・協議に対する経営側の基本姿勢」である。報告書の半分近くのページを割いて、労使交渉で問題になりそうな点を例年に比べて丁寧に説明している。
労働側が定昇・賃金カーブ維持相当分(2%)を確保したうえで「1%以上の賃上げ(月例賃金の引き上げ)を求めている点について、「我が国経済の好循環実現が必要であるとの見地から企業収益の改善を、さらなる成長への投資に振り向け、設備投資や雇用の増大、賃金の引き上げにつなげていくために労使は、より幅広い視野に立って議論を深めていく姿勢が求められる」とし、「競争に勝ち抜く新たな付加価値を生み出す従業員のモチベーションや士気を高める観点から、業績が好調な企業は設備投資だけでなく、雇用の拡大、賃金の引き上げに振り向けていくことを検討することになる。その際の賃金の引き上げについてはここ数年と異なる対応も選択肢となり得よう」とベースアップにも含みをもたせた書き方になっている。
賃上げというと一般的には基本給の引き上げと考える向きが多いが、報告書の中で、「賃上げとは何か」という項目で、賃金について、労働基準法第11条「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」との考え方をベースに賃金制度や賃金体系も含めて経営側が理論構成をしている点に注目する必要がある。そのことが、次の経営側の基本的考えにつながっているということである。
すなわち「賃金などの労働条件は自社の経営状況に即して労使が徹底的に議論して決定するもので、賃金は基本給をはじめ、諸手当、賞与・一時金、福利厚生費なども含めて、すべての従業員にかかわる総額人件費を適正に管理する観点から自社の支払い能力に基づき判断・決定するという原則は揺るがない」としている。そのことは、賃上げについてどのように対応するかは、従来同様、各企業の支払い能力、適正な総額人件費管理を踏まえて自己責任で対応すべきとの基本原則を述べたものと理解される。また、報告書では、一人一か月あたりの総額人件費は所定内賃金を100に対して賞与・法定福利費等を含む総額人件費は164.6と約1.65倍になるとしている。基本給を上げると他の制度の費用も増加するため、経営側もその引き上げには慎重になっているのが実態だ。
世間では今次労使交渉で賃上げ(ベースアップ)をするかどうかが注目されているが、賃上げにはいろいろな方法があり、経営状況や従業員のモチベーション等も考慮して、どのような対応が可能か労使は十分話し合うことが大切としている。
昇給制度のあり方も最近労使間の大きな課題になっている。経営側からは年功的賃金から能力、職務、役割、成果等を反映した賃金制度が多く導入されている今日、従来型の定期昇給制度はうまく機能せず、見直す必要があるとの話が高まっている。報告書の中でも「近年において勤続・年齢に応じて自動的に昇給する部分は減少する一方、査定昇給が高まっている」と指摘するとともに、定期昇給制度そのものを廃止した企業があるなど賃金制度の変容で昇給制度の考え方や仕組みが多様化していると指摘している。
労使交渉でよく問題になるマクロの労働分配率については、トピックスで「マクロの労働分配率は報酬決定の基準にはならない」との表題で解説している。
「労働分配率は企業の付加価値に占める人件費の割合であるが、一般に景気後退局面では分母である企業の付加価値額が減少する中にあって雇用維持努力がなされ、分子である人件費が比較的安定して推移することから、結果として分配率は高まることになる。一方で、景気拡大局面では、その力強さによって分母の付加価値額が大きく高まるため、労働分配率は低下することになる。そのため、わが国の場合、労働分配率は、景気と逆相関の関係になる」。つまり、労働分配率は、景気動向とわが国の雇用制度の関係が関わっていることも理解しておく必要がある。「ミクロベースの個別企業の労働分配率は装置産業よりも労働集約産業の方が高い特徴がある。業種や事業規模などによってもその水準は大きく異なるため、業種・業態等が異なる他企業の労働分配率と比較することは、必ずしも報酬決定の参考にならない。
さらに、同一産業にあっても人員構成が異なれば、水準自体も異なることに留意が必要である」としている。従業員の賃金水準は、企業の生産性や支払い能力の高低が影響するが、一般論として言えば、労働集約型企業は労働分配率が高く、装置型企業は労働分配率が低いが、一人当たりの賃金水準は装置型産業が労働集約型企業より高いなど、分配率の高さと賃金水準は常に同じではないことも理解しておく必要がある。
今年の労使交渉で、増加している企業の内部留保や、企業が保有する現金・預金の一部を賃上げに回すべきとの指摘があることに対して、報告書のトピックスで「内部留保の確保は企業の持続的成長に不可欠」というタイトルで経営側の考えが詳しく述べている。少し長くなるがポイントと思われる点について紹介しよう。
「内部留保とは、企業活動の成果として得られた当期純利益から配当などの社外流出を差し引いた剰余金の残高の累計であり、貸借対照表のうえでは、利益剰余金などを指している。近年の推移をみるといずれの規模においても、利益剰余金が増加していることが確認できる。内部留保は会計上の概念であり、その実態は現金・預金などではなく、主に機械設備や研究開発、新たな事業への投資に充てられている。また融資を受ける際に財務体質の健全性が問われるため、近年の増加は世界金融危機などを受けて、企業が財務体質の改善を進めた結果であるとも言える。
現金・預金は、企業内における蓄えというより、日々の営業資金という性格が強い。多くの企業は買掛金の支払いや借入金にかかる利払い・元本の償還など、一定期間に必要となる最低限の資金を、最も流動性の高い現金ということ形で確保している。
また、企業は利益水準にかかわらず従業員などへの報酬支払いのほか、社会保険料の納付を行うなど一定の現金・預金を絶えず保有しておかなければならない。その現金・預金を賃上げの原資にすべきとの議論は、非現実的な議論と言わなければならない。
内部留保は、事業環境が激変し、業績が大きく悪化した局面にあっても、債務超過による経営破綻を回避するための備えを講じることが極めて重要である。したがって、内部留保を適正水準に維持していくことこそが、企業の持続的な事業運営を可能とし、ひいては従業員の雇用の安定や労働条件の向上に結び付くことになる。こうした事実や内部留保を巡る誤解を解いていくために、企業は積極的に理解を求める努力をしていく必要がある」と述べている。
今後の経済経営環境や人材の活用について第1章、第2章で述べている。第1章は「わが国企業を取り巻く経営環境と経済成長に向けた課題」とし、6重苦とか7重苦と言われてきた課題の一部はまだ残されているが、「経営環境は大幅に改善した。今後、持続的な経済成長をしていくためには、規制改革の断行、TPPをはじめとした経済連携の推進など成長戦略の着実な実行が不可欠」としている。第2章「多様な人材の活用」では企業のダイナミズムをもたらすのは「人」であるとし、「雇用・労働市場の改革とあわせて、生産性の向上やイノベーション創出に向け企業の人材戦略は極めて重要」して、ダイバーシティに注目し、多様な人材の活用を推進するうえでの留意点などについて書かれている。
経済・経営環境が複雑化し、企業が取り組むべき課題が多々あることや丁寧に書きたい点も大事ではあるが、要点整理とポイント重視の記述を心がけることで頁が圧縮され、理解度が高まるのではないかというのが読後の感想である。
【MMC総研代表 小柳勝二郎】