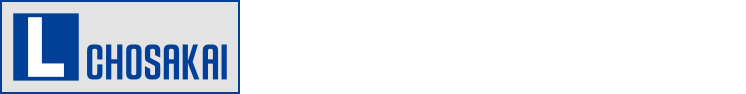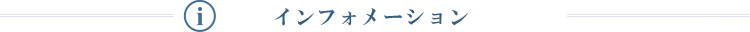労働あ・ら・かると
官邸筋が2029年度中に最低賃金1,500円目標掲げる 果たして、その実現は可能か、政労使はどう取り組む
労働評論家・産経新聞元論説委員・日本労働ペンクラブ元代表 飯田 康夫
〇時は令和7年5月22日。舞台は、東京都千代田区永田町の首相官邸。ここに政労使のトップリーダーである石破首相、芳野連合会長、十倉経団連会長(当時)らが顔を揃え、2025春闘での労使交渉、中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の施策パッケージ案及び最低賃金の引き上げ方針を巡って意見交換が行われた。
〇労使代表から2025春闘でも2024年に続いて5%台の高い賃上げが実現できたことが報告され、これを受けて石破首相は語る。
〇「2024年11月の政労使意見交換の場でベアを念頭に大幅な賃上げへの協力をお願いし官民で連携して取り組まれ、その結果、2025春闘・労使交渉で、賃上げは、33年ぶりの高い賃上げ水準となった昨年をさらに上回る水準にあり、2年連続で5%を上回っている。この賃上げの趨勢がわが国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者、地方で働く皆さまにも行きわたることが重要だ。賃上げこそ成長戦略の要であり、2029年度までの5年間で、実質賃金を(毎年度)1%程度の上昇を賃上げの新たな水準の社会通念、ノルムという言葉を使うが、わが国に定着させ『賃上げと投資が牽引する成長型経済』を実現するため、『賃金向上推進5か年計画』に基づき、中小企業・小規模事業者の経営変革の後押しと賃上げ環境の整備に政策資源を総動員する」と語り、成長型経済の実現のカギを握る2本柱の一つが賃上げであることを強調したといえる。
〇これに続いて「最低賃金引上げの目安」について語る。
〇「適切な価格転嫁と生産性向上支援により、最低賃金の引き上げの後押しをし、2020年代に全国平均1,500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、最大限の取り組みを5年間で集中的に実施する」と強気の構えだ。最低賃金1500円目標ということは、2024年度の最低賃金全国平均は1,055円。これを目標の1,500円を実現するには、この5年間で445円の引き上げ増額が必要で、単純計算しても毎年89円、7.3%の伸びが求められる。果たして、政労使はこれにどう取り組むというのか。
〇石破首相はさらに語る。「中央最低賃金審議会の目安答申を上回る地方には、補助金を交付したい」と表明、「EU(欧州連合)指令では、賃金の中央値の60%や平均値の50%が最低賃金改定に当たっての参照指標として、加盟国に示されている。わが国と欧州とでは制度の一部に異なる点があることを留意しつつ、これらに比べてわが国の最低賃金が低い水準となっていることも踏まえ、中央最低賃金審議会において議論を頂く。その上で、各都道府県審議会で、中央最低賃金審議会の目安を超える最低賃金に引き上げが行われる場合への特別な対応として政府の補助金における重点的な支援、交付金などを活用した都道府県による地域の実情に応じた賃上げ支援の十分な後押しにより、生産性向上に取り組み、最低賃金の引き上げに対応していただく中小企業・小規模事業者を大胆に後押ししていく。地方最低賃金審議会においてこれらの政府全体の取り組みや各都道府県の賃上げ環境も踏まえ議論していただく。地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げるなど地域間格差の是正も図る」とする。
〇春闘同様、官邸主導型ともいえる2029年度中に最低賃金の引き上げ目安を1,500円という官邸筋の高い目標に労使はどう対応するというのか。最低賃金の引き上げ目安の審議は、学識経験者に労使代表が参加しての三者構成による中央最低賃金審議会で議論され、目安が決まる仕組みだが、官邸筋の引き上げ目安がそれら重要な審議会に先立って目標額が提示されるという異例の逆転現象に不満の声も聞かれる。労使の意見を聞く前に1,500円が独り歩きし、労使の見解が正式の場で表明される前段階で、ルール無視だという声も漏れてくる。
〇では、労使は中央最低賃金審議会が開かれる事前の段階で、どのような見解を明らかにしているのか。連合は,厚生労働大臣宛の要請書を手交、使用者団体も4団体連名で要望をまとめ公表した。
〇連合 中期的に大幅な水準引上げを求む
〇労働側の連合は6月3日、「最低賃金行政に関する厚生労働省への要請行動」を展開、「連合は、賃上げが当たり前の社会を目指し2025春闘では、全力で取り組み、最低賃金は社会全体に賃上げの流れを広げていくこと、労働組合のない企業労働者へも確実に波及させるために欠かせない、最低賃金近傍で働く人の生活と安心を確保し、誰もが希望を持てる社会を目指し、最低賃金の確実な引上げとその履行確保を徹底されたい」とし、要請文を手交した。一方、使用者側も4月17日時点で、中小企業4団体連名(日本商工会議所、東京商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)で、「最低賃金に関する要望」を公表、中小企業・小規模事業者の経営実態を踏まえた政府方針検討・審議決定を主張している。労使の主張点のポイントは次のようだ。
〇連合は、要請行動の中で、「地域別最低賃金の水準については、憲法第25条、労働基準法第1条、最低賃金第1条を踏まえ、経済的自立を可能にし、人たるに値する生活を営なむ賃金水準とする必要がある。国際的な最低賃金の流れとして相対的な貧困水準(一般労働者の賃金中央値60%など)が重視されていることも念頭におきつつ中期的に大幅な水準引き上げをめざすこと」を最優先課題として掲げる。
〇次いで、「地域別最低賃金の早期発効に向けて、それは全労働者の利益である。そのため、中央最低賃金審議会への諮問、目安に関する小委員会の開催及び答申の日程設定は10月1日を軸に、より早期の発効に最大限配慮すること。同時に各地方労働局に対しても中央最低賃金審議会の審議や答申の丁寧な周知と共に早期発効の趣旨を踏まえた審議会運営が図られるよう指導を徹底すること」を要請した。
〇使用者側の4団体 納得感のある審議決定
〇一方、中小企業4団体連名による「最低賃金に関する要望」では、次のような内容を公表している。
〇「雇用の約7割を支える中小企業・小規模事業者の自発的・持続的な賃上げが不可欠だ」。他方「最低賃金は労働者の生活を保障するセーフティーネットであり、法定三原則(生計費、賃金、企業の支払い納涼)に基づく納得感のある審議決定が求められ、賃上げの政策的手段として用いることは適切ではない」。「物価高の中、ある程度の引き上げは必要と考えるが、企業の経営実態を踏まえない引上げは、地方の産業。生活インフラを支える中小企業。小規模事業者の事業継続を脅かし、地域経済に深刻な影響を与え、地方創生の実現に支障を生じかねない」と前置きした上で、6項目にわたる最低賃金に関する要望を要旨,次のように列記する。
〇① 最低賃金に関する政府方針を示す場合には、中小企業・小規模事業者を含む労使双方参加の場での議論を
〇② 法定三要素に関するデータに基づく明確な根拠のもと、納得感のある審議決定を
〇③ 中小企業・小規模事業者が自発的・持続的に賃上げできる環境整備の推進を
〇④ 中小企業・小規模事業者の人手不足につながる「年収の壁」、問題の解消を
〇⑤ 改定後の最低賃金に対応するための十分な準備期間の確保を
〇⑥ 産業別に定める特定最低賃金制度の適切な運用を
〇最賃引上げ目安 100円台が実現するか
〇果たして最低賃金1,500円を実現するには、2024年度の全国平均額である1,055円との差額455円を前提に考えると、毎年引上げ目安額は89円が浮上してくる。2025年の引き上げ目安が60円、70円を想定するとして、仮に60円アップの目安であれば全国平均は2,115円となり、2026年度には1,500円との差額は、395円となる。これを4年で1,500円を実現するには毎年、約100円近い引上げ目安答申が必要となり、2020年代中(2029年度)に思い切った目安の答申が可能なのか。これが実現しても国際的には日本の最低賃金は下位にあるという現実にかわりはない。
〇昨今の求人広告・チラシをみると、時給1,200円、時給1,300円、時に1,500円台の募集をみることがある。時代は、間違いなく時給1,500円時代を迎えつつあるようで、それに対応できる企業体質づくりが求められているように思う。
〇最賃引上げ「影響」「負担感」 地方中小企業で深刻
〇参考までに日本商工会議所と東京商工会議所が3月5日に公表した「中小企業における最低賃金の影響に関する調査」から中小企業の経営実態を紹介したい。
〇調査は、全国47都道府県から3958社、389の商工会議所から回収。中小企業における最低賃金引上げの影響や政府目標への受け止めについて、その実態が明らかにされた。
〇最低賃金引上げ50円の目安が示された2024年の最低賃金引き上げの「影響」、「負担感」を尋ねたところ、都市部に比べ地方で深刻な状況にあることが明らかになっている。2024年の最低賃金引き上げにより、最低賃金を下回る従業員がいたため、賃金を引き上げた企業は44.3%。地方では半数近く(46.4%)に達し都市部(32.4%)より14㌽高い。最低賃金の「負担感」について、「大いに負担」・「多少は負担」は合わせて76%、地方では8割近く(77.5%)に達し、都市部(67.9%)より9.6㌽高い。
〇新たな政府目標(1500円)について、「対応は不可能」(19.7%)・「対応は困難」(54.5%)は、合わせて74.2%と7割を超えた。特に地方・小規模事業所の4社に1社が「対応不可能」と回答。2025年度から7.3%引き上げとなれば、「収益悪化により事業継続が困難」との回答が15.9%。対応が可能な引上げ水準ついては「1%未満」から「3%程度」までの合計が67.9%と約7割。7%程度、8%以上引上げは、僅か1%だ