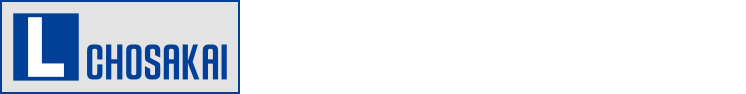労働あ・ら・かると
海外在宅勤務の経験から日本の「働き方」を考える
イギリス在住
大野 美希子
働き方改革の一環で「在宅勤務」「テレワーク」という言葉を目にすることが増えた。ご自身の勤める企業が新たに「在宅勤務制度」を導入・拡充したという方もいるだろう。一方、「自分には特に関係のない制度」と思っている方も少なくないのではないだろうか。実は私もその一人であった。
私が在宅勤務を開始したきっかけは、夫の海外転勤であった。突然「仕事か家族」の選択を迫られ、大いに悩んだ結果、会社から提示されたのは「海外在宅勤務」という案であった。
当時私が勤めていた日系大手企業では、月8日の在宅勤務が認められていた。「海外在宅勤務」とは、この制度の範囲で、所属部署を変更せずに、イギリスで仕事をするというものである。現在の仕事をそのまま継続できるこの案は、私にとって画期的な打開策であった。
配偶者転勤による退職を防ぐための「休職制度」を導入する企業も増えている。しかし、場所さえ問わなければ継続して働きたいという人は多い。イギリスでも配偶者転勤により退職・休職中の日本人をよく見かけるが、仕事を続けたかったという声は頻繁に聞く。女性の管理職が増えていく中、男性が配偶者転勤により選択を迫られる機会も今以上に増えるだろう。ある企業の方は、外国人従業員の長期帰省のニーズに「海外在宅勤務」が有効だと話していた。
しかし「海外在宅勤務」の実施にはまだ課題も多い。私が最も苦労したのは、長距離・長時間の移動であった。在宅勤務日数が短いほど、渡航の経済的・肉体的負担は大きい。
長期の在宅勤務が可能であれば、移動負担は軽減される。しかし今度は運用面での課題が出てくる。在宅勤務制度がある企業でも、一部の先進的な企業を除けば、従来通りの職場慣行を続けていることは多い。例えば「在宅勤務者の代わりに電話や指示を受ける」「在宅勤務時は一人でできる仕事をする」等はよく聞く話だ。これは在宅勤務者がまだ「ほんの一部」で「週1~2日」という場合が多いためだ。しかし「月1~2週間」となると、途端に立ち行かなくなる。
「海外在宅勤務」では時差もある。在宅勤務の導入企業が、社員の在席状況を常時ITツールで確認しているという事例を耳にする。しかし日本企業が慣れ親しんでいる「時間やプロセスによる管理」は、時差があれば難しくなる。
「海外在宅勤務」の実践で気づいたこれらの課題は、実は「在宅勤務」や「働き方改革」そのものの課題である。なぜなら在宅勤務者が増え、それに伴いメンバーが異なる時間に働く「フレックス勤務」が増えれば、同じ問題が起こるからだ。政府が後押しする中、在宅勤務者の比率が更に高まれば、在宅勤務者の仕事をオフィスにいる人が肩代わりし続けるのは難しくなる。また、全社員の勤務可能な時間帯に仕事のプロセスを管理していては、管理職の長時間労働を招き本末転倒だ。
本当に「働き方改革」をするならば、どこでも、いつでも、誰もが同じように仕事ができるようにすることが重要だ。しかしそれは、制度やITシステムを整えればできることではない。手書きサイン・印鑑なども含めた紙の資料の存在、つい目の前にいる人だけに伝えてしまう重要な情報、働いている姿を見ることが主体の労務管理。オフィス勤務時は当たり前で気づかない、各職場のちょっとした慣習や思い込みが、乗り越えるべき課題となる。
「海外在宅勤務」を経て、最終的に私は退職を選んだ。家族との暮らしと仕事を両立できる素晴らしい策であったが、月8日の上限の中、頻繁な移動による経済的・肉体的負担はあまりにも大きかった。
しかし、数年もすれば、上限日数を撤廃する企業は増えていくだろう。海外も含めた「在宅勤務」を成功させる上で私が最も重要かつ難しいと考えるのは、職場の慣習を変えられるかということだ。欧米ではテレワークが特別な人のものではなく、自然に取り入れられている。日本でもそのような姿をめざすなら、長年培われてきた職場の文化という難しい課題に切り込む覚悟が必要となる。
そもそもなぜ、企業が「在宅勤務」を推進するのか。主な理由は、多様な人材の確保が、今後の労働力不足を解消し、企業の成長にもつながるためだ。しかしこの果実は、形を整えるだけでは手に入らない。経営者だけでなく、組織の一人一人がこの意義を理解し、各職場における「当たり前」に変化をもたらす必要がある。
今回私が体験した「海外在宅勤務」は「在宅勤務」の中でもやや特殊な事例かもしれないが、「働き方改革」のその先を考える上で、役に立つものだと確信している。近い将来、多くの企業と人々が、この果実を手に入れることを願っている。
以上